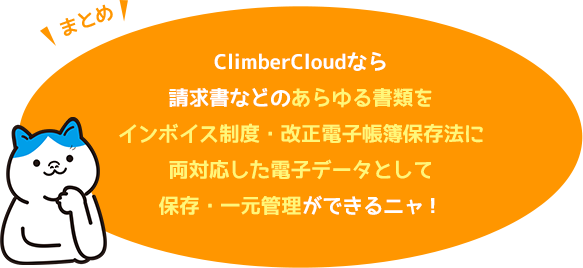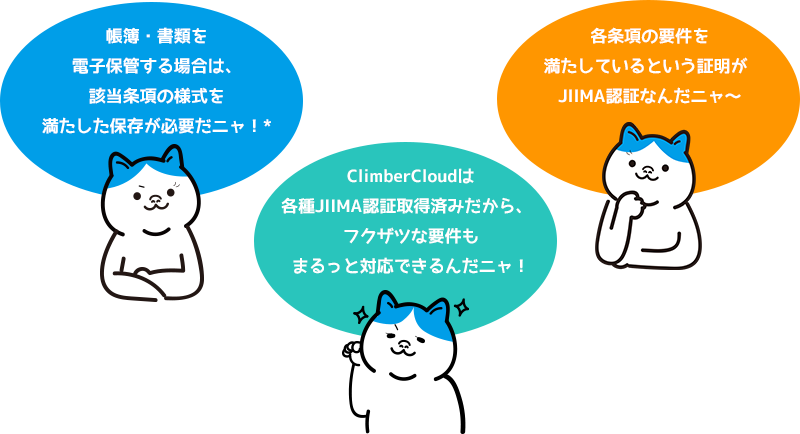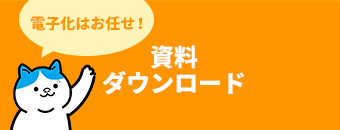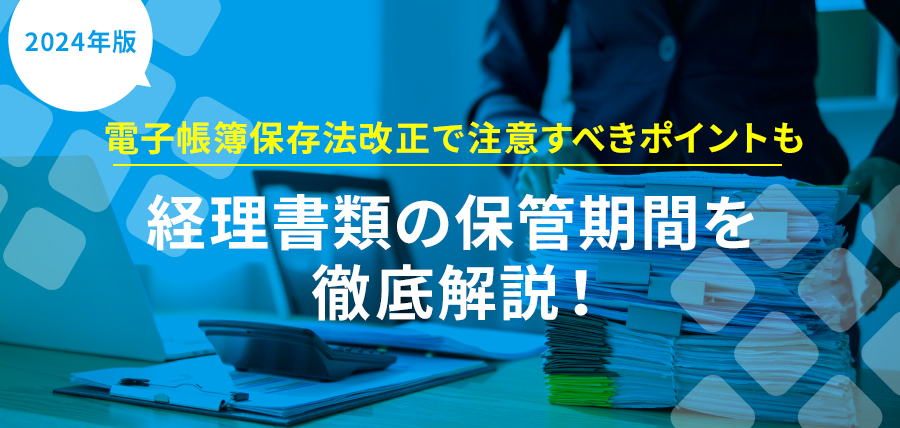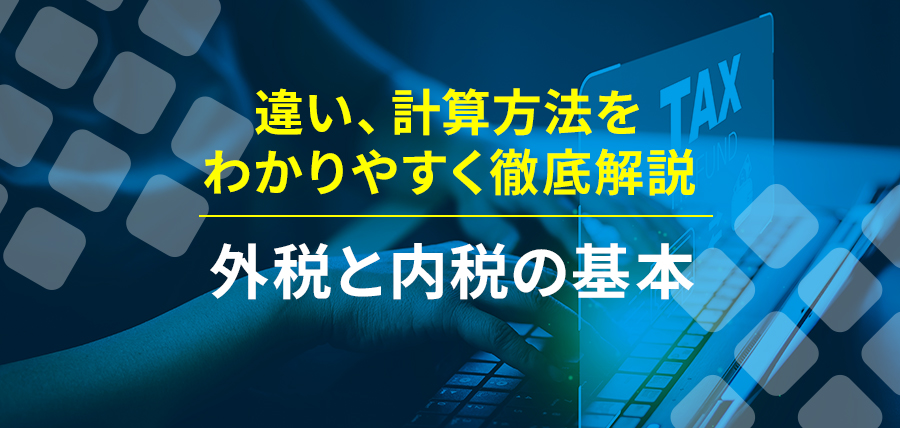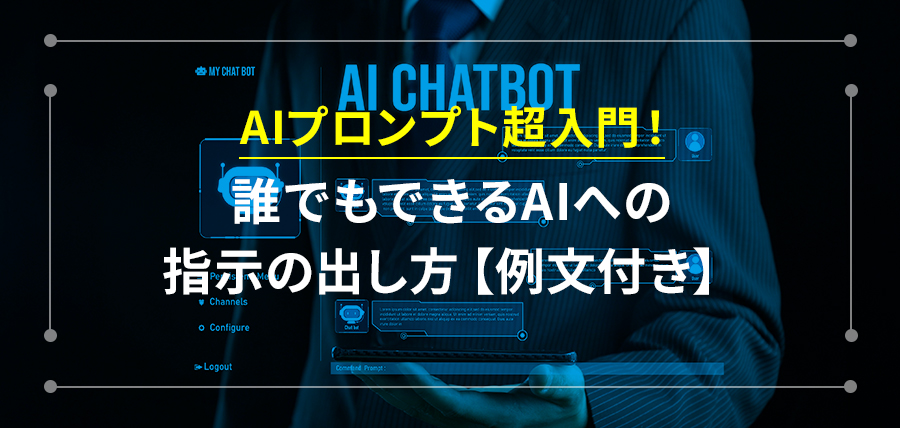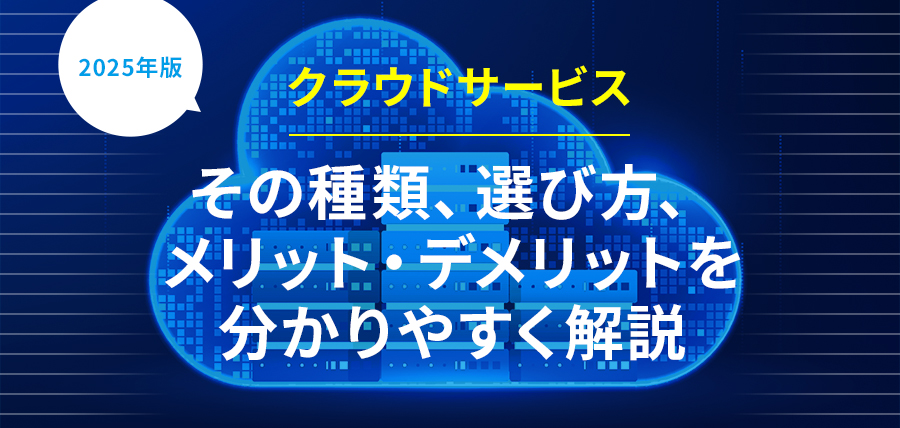01
会計ソフトのAPI連携が経理業務の「ゲームチェンジャー」である理由

会計ソフトのAPI連携によって業務が自動化され、大幅な効率化が期待できます。API連携は単調な作業の多い経理業務において、大きな変革のカギとなります。
API連携によって、複数のツールを行ったり来たりすることなく、自動的にデータの共有が可能です。業務によっては「手入力ゼロ」も決して不可能ではありません。
今さら聞けない「API連携」とは?管理職が部下に説明できるレベルで解説
API連携とは、異なるツールに保存されているデータを、スムーズに共有できる仕組みです。ツール間のデータ連携を自動で行うための公式な接続口といえます。
例えば、会計システムと経費精算システムはそれぞれ独立したツールであり、本来であれば同じ取引について両法での入力が必要です。しかし、両者間でデータを共有できれば、面倒な入力作業が一度で完了します。また、経費申請から上長の承認、経費の払い戻し、経費の計上と払い戻しの仕訳まで、まるで1つのツール上で処理されているかのように進みます。
なぜ「手入力ゼロ」が実現可能になるのか?データ自動取得・自動仕訳の仕組み
データの手入力が不要となる理由は、データの自動取得や自動仕訳の機能があるためです。
会計ソフトの多くは、金融機関やクレジットカード会社、他のツールなどと連携することで、お金の動きに関するデータを自動で取得できます。専用のボタンをクリックすれば自動でデータの取得が開始されるものや、週2回など自動更新が設定されている会計ソフトもあります。
自動仕訳は、連携によって取り込んだデータについて、仕訳のルールに従い自動で仕訳を行います。自動仕訳について経理担当者が内容を確認し、問題がなければ登録すると仕訳が完了します。問題があった場合は経理担当者が修正する必要があります。しかし、多くの会計ソフトは修正からルールを学習してそれ以降の仕訳に反映させるため、仕訳の精度が上がり手入力の頻度は下がると考えられます。
【メリット・デメリット】導入前に管理職が押さえるべきAPI連携の光と影
API連携によって得られるメリットは大きいものの、万能ではありません。API連携のメリットとデメリットは次の通りです。
メリット
- ・業務を効率化できる
- ・人的ミスを削減できる
デメリット
- ・導入コストがかかる
- ・セキュリティが必須である
- ・インターネットが使えなければ連携できない
取引に関する重要な情報は外部に漏れることのないようにしなければなりません。多くの会計ソフトでは次のような対策を行っているため、安心して利用できます。
・2段階認証
・IPアドレスによる接続制限
・ログイン試行回数の制限
・バックアップ機能
・更新履歴の記録・保持
・第三者認証の取得
・脆弱性や安全性に関するテストの定期的な受診
・セキュリティシステムによる不正アクセス防止や自動監視






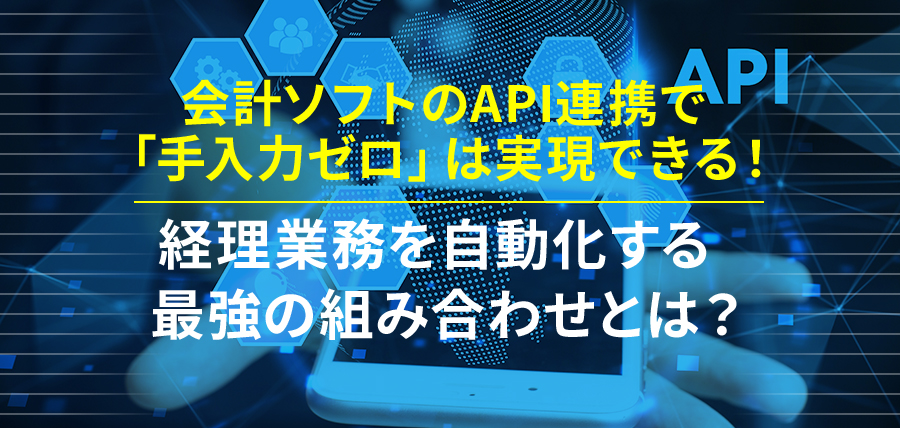




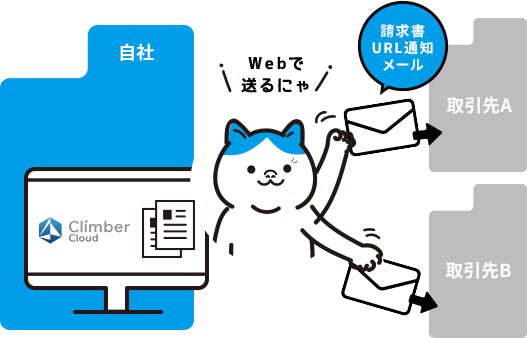
![データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ 自社による保存機能 ]](/article/category_system/img/whatisinvoice/article07_pic03.png)
![データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ Web受領サービス(書類受領) ]](/article/category_system/img/whatisinvoice/article07_pic04.png)