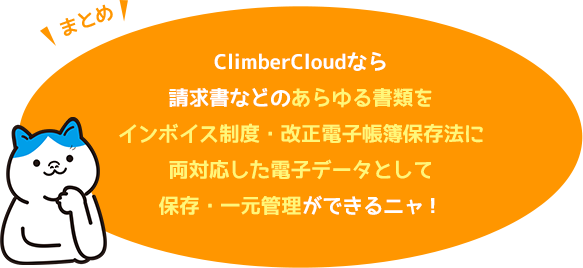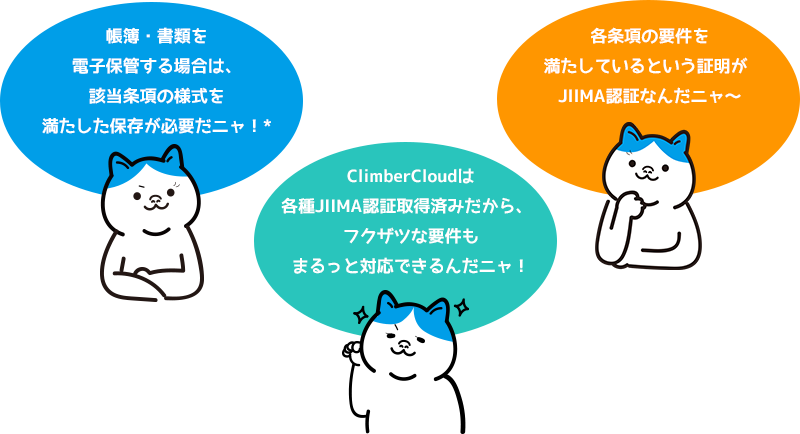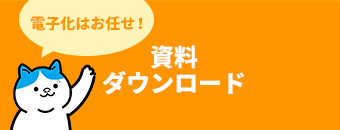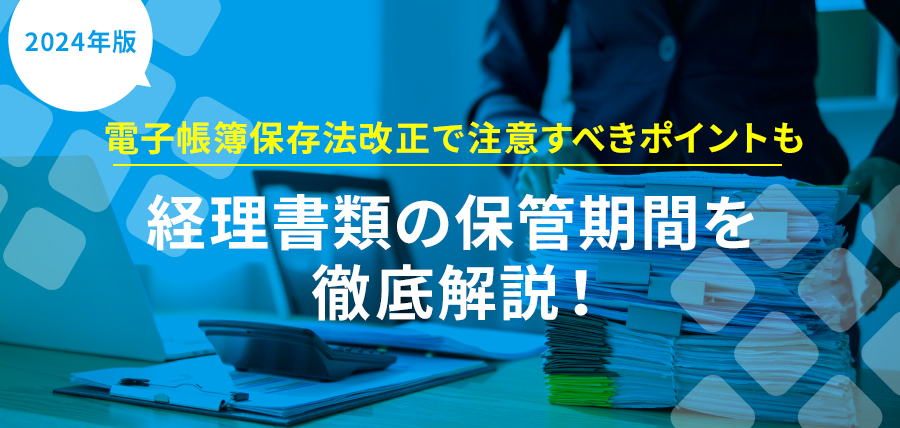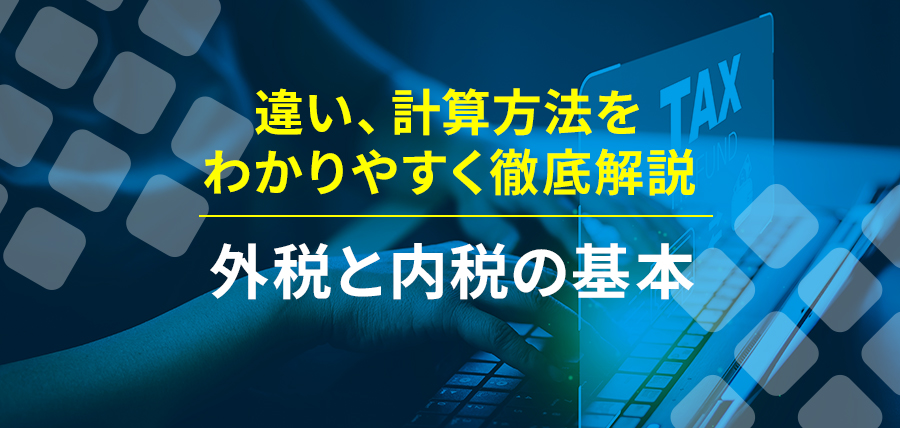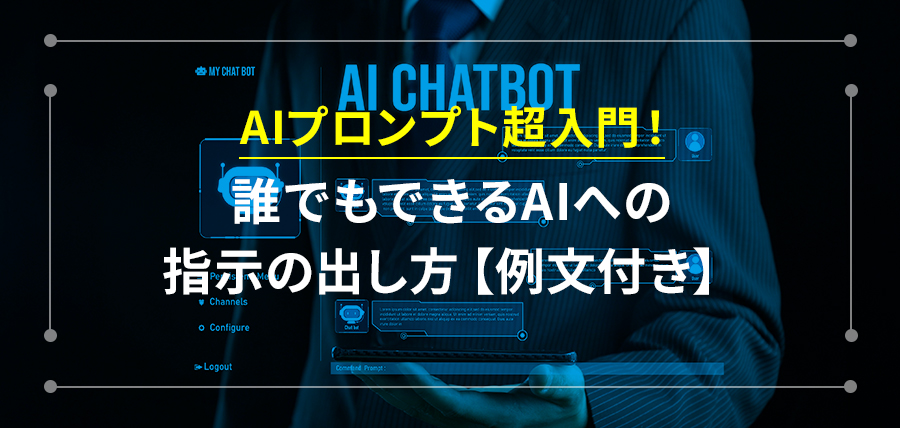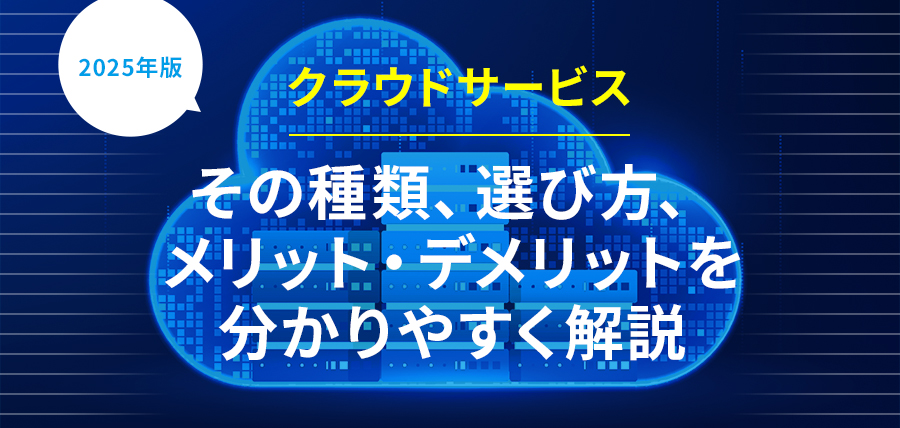「オンプレミスとクラウド、どっちがいいの?」という疑問を解消するために、以下では5つの観点からそれぞれの特徴を解説し、両者を比較します。
コスト
システム導入にかかるコストは、初期費用と運用費用の2つに大きく分けられます。以下では、オンプレミスとクラウドのコストを比較してみましょう。
| 種類 | 初期費用 | 運用費用 |
|---|
| オンプレミス | 高くなりやすい | ・月々の支払いは基本的に不要だが、保守費用が掛かる場合も
・機器が稼働するための電気代や保守管理にかかる人件費が必要 |
| クラウド | 安く抑えやすい | ・サービス内容に応じた従量課金制で、月々の支払いが必要 |
オンプレミスの場合は、使い始めるために機器をそろえたりソフトウェアを購入したりと、初期費用は高額になります。金額には幅があり、システムによっても異なりますが、数百万円から数千万円の費用がかかることもあります。
オンプレミスの運用費用については、基本的に自社で行うため必要ありませんが、購入したソフトウェアなどの保守を依頼する場合には保守費用がかかります。また、自社でシステムを管理するスタッフの人件費や、サーバやハードウェアが稼働するための電気代、機器の寿命を考慮した交換や更新などの費用がかかります。
クラウドの場合は、機器やソフトウェアはサービス提供者が準備するため、オンプレミスほどの初期費用は掛かりません。初期費用が無料のサービスもあります。
一方で、クラウドは従量課金制のサービスが一般的であり、使い続ける限り継続して運用費用が発生します。但し、使用した分だけ支払う料金体系のため、コスト面での無駄がありません。
しかし、クラウドであっても、使用している間はコストを払い続ける必要があるため、長期的な視点で見るとコストが高くなる場合もあります。
事業の規模やサービスの内容によって、コストパフォーマンスは違ってきます。
結果的に、クラウドの方がオンプレミスより割高になる場合もあるため、事前の料金シミュレーションが必要です。
セキュリティ
オンプレミスとクラウドでは、セキュリティ対策を誰が行うかという点で違ってきます。
| 種類 | セキュリティ対策 |
|---|
| オンプレミス | 自社で行う |
| クラウド | サービス提供者が行う |
オンプレミスでは、セキュリティ対策を自社で行う必要があります。セキュリティについて知見のある人材がいれば、堅牢性の高いセキュリティを構築できるでしょう。しかし、そうした人材がいない場合は外部に依頼する必要があり、その分のコストがかかります。
但し、オンプレミスは常時インターネットに接続しているわけではないため、情報漏洩のリスクは低いといえるでしょう。
クラウドでは、サービス提供者による高度なセキュリティ対策が施されています。セキュリティの知見を持つ担当者が社内にいなくても、一定レベルのセキュリティが担保されています。
しかし、インターネット上に重要な情報が流れるため、情報漏洩のリスクはゼロではありません。
サービス提供者側の管理体制における不備や、誤操作による情報漏洩なども、リスクとして考えられます。
事前にセキュリティに関してサービス提供者側に確認しておくとよいでしょう。
運用・保守
システムを使う中で、運用や保守を行う必要があります。トラブルがあった場合の対応やアップデートも必要です。こうした管理について、オンプレミスとクラウドを比較してみましょう。
| 種類 | 運用・保守 |
|---|
| オンプレミス | 自社で行う |
| クラウド | サービス提供者が行う |
オンプレミスの場合は、基本的に、運用や保守を自社で行わなければなりません。システムに精通した人材が社内にいる場合は、オンプレミスの方が運用やトラブルへの対応がしやすいでしょう。一方で、システムに精通した人材がいない場合は、トラブルが起こったときに早急な復旧が難しくなります。運用や保守を外部に委託している場合は、追加のコストがかかる点にも注意が必要です。
クラウドの場合は、運用や保守、障害対応、アップデートまで、サービス提供者が対応します。トラブルの解消やバックアップの処理なども任せられるため、運用の負担をなくすことができます。
24時間365日の運用サポートを受けられるクラウドシステムもあるため、万一の場合でも安心です。
柔軟性・拡張性
自社に合わせて柔軟にシステムを構築できることや、必要に応じて拡張させられることも、システム選びにおいて大切な要素です。この点について、オンプレミスとクラウドを比較してみます。
| 種類 | 柔軟性・拡張性 |
|---|
| オンプレミス | 自社に合ったものを開発可能だが、時間や費用がかかる |
| クラウド | 限界はあるが、リソースの増減を迅速・柔軟にできる |
オンプレミスでは、自社の業務フローに合わせて自由度の高い開発が可能で、独自のカスタマイズができます。社内の別のシステムとも連携させやすい点がメリットです。
しかし、オンプレミスでシステムの拡張などを行う場合は、開発・設定や設備の買い足しが必要なため、コストがかかります。また、開発にある程度の時間が必要となる場合もあるでしょう。
クラウドでは、契約内容やプランを変更するだけで機能の内容を変えられます。ビジネスの拡大や環境の変化に迅速に対応できるでしょう。但し、提供されるサービスの範囲内でしか変更できないため、自社に最適な環境を構築できない可能性はあります。
クラウドではインターネットを通じて他システムとの連携を行うため、システムによっては連携できない場合もあります。
アクセシビリティ
オンプレミスとクラウドでは、アクセスのしやすさや条件も以下のように異なります。
| 種類 | アクセシビリティ |
|---|
| オンプレミス | 社内でのアクセスがメインとなる |
| クラウド | インターネット環境とデバイスがあれば社外からでもアクセスできる |
オンプレミスのシステムは、社内ネットワークに接続しなければアクセスできません。特定の場所からしか操作できないため、アクセシビリティは低いといえるでしょう。社外からオンプレミスのシステムにアクセスすることも可能ではありますが、VPNや閉域網、専用線などを設定し、安全性の高い方法を確立する必要があります。
クラウドのシステムであれば、インターネット経由でいつでもどこからでもアクセスできます。
パソコンのほか、スマートフォンやタブレットなど、デバイスを問わずアクセスできることもメリットのひとつです。
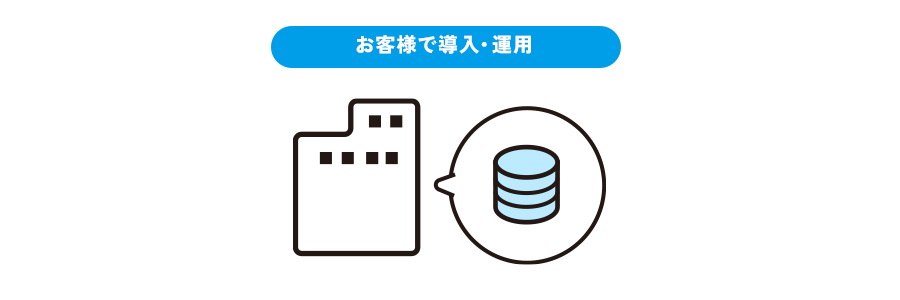






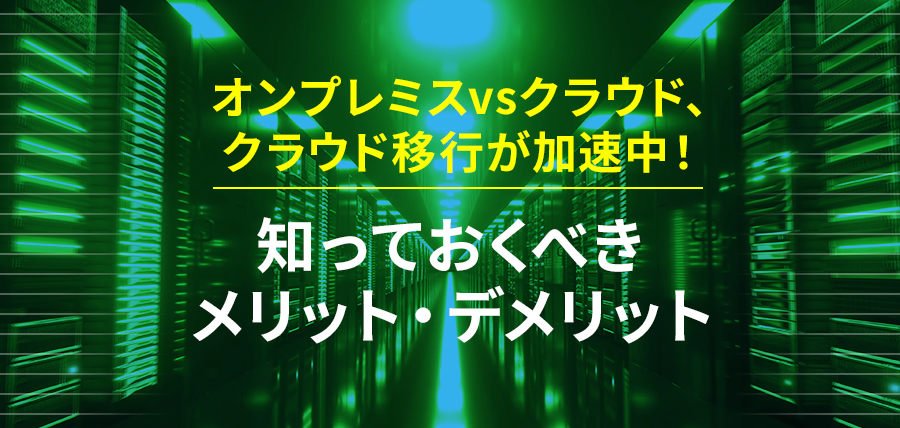
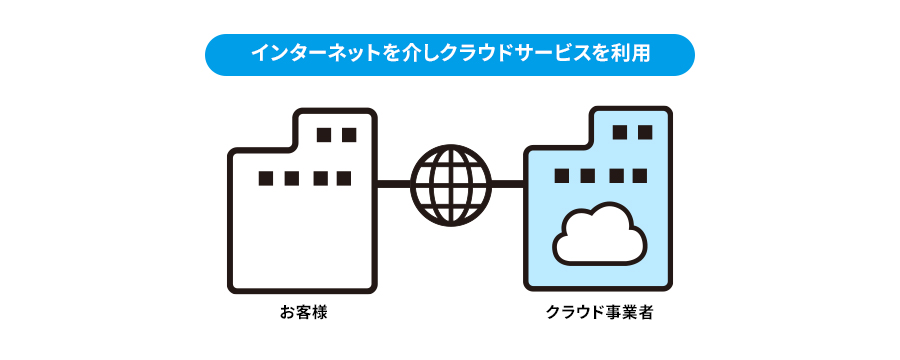





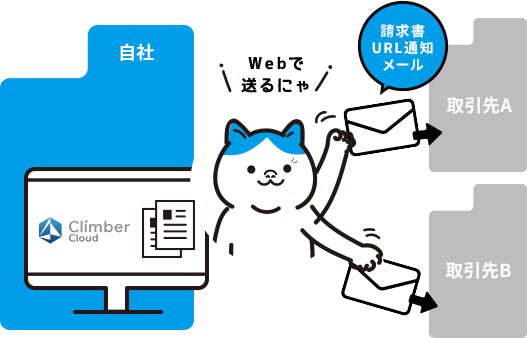
![データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ 自社による保存機能 ]](/article/category_system/img/whatisinvoice/article07_pic03.png)
![データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ Web受領サービス(書類受領) ]](/article/category_system/img/whatisinvoice/article07_pic04.png)