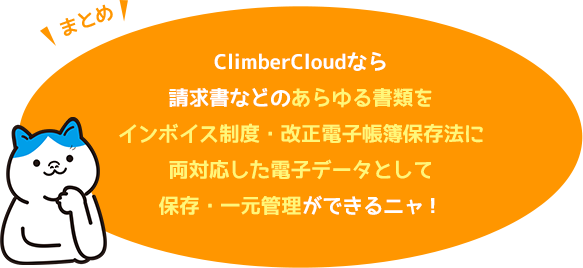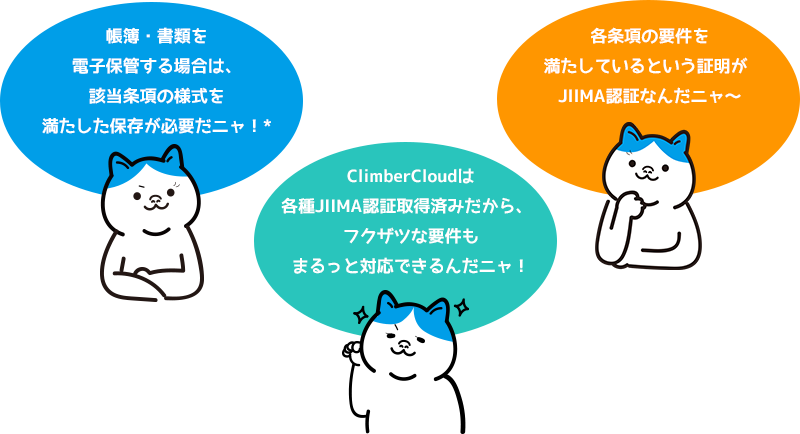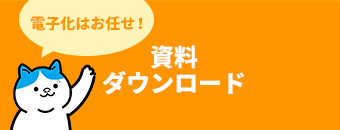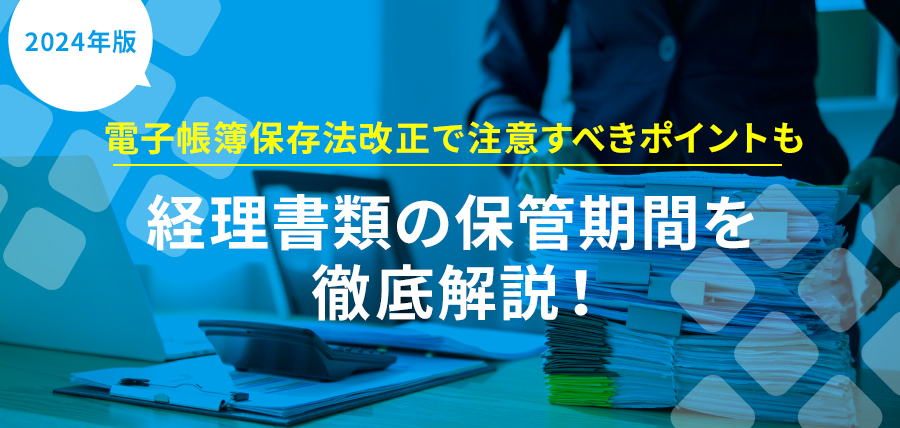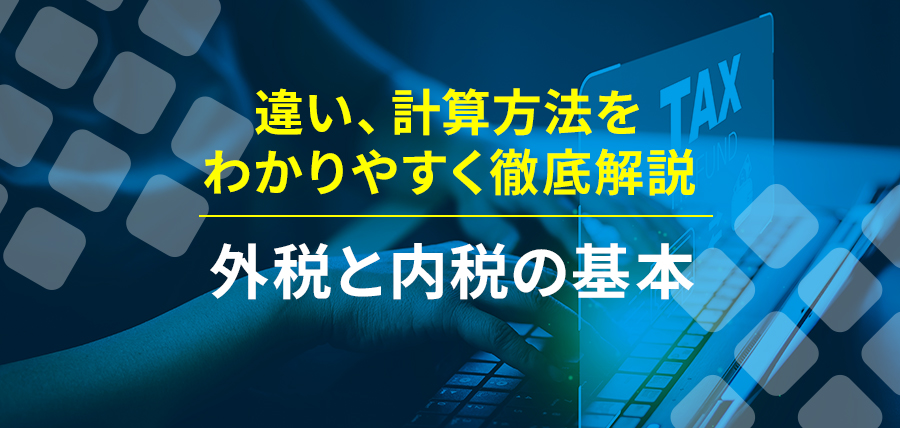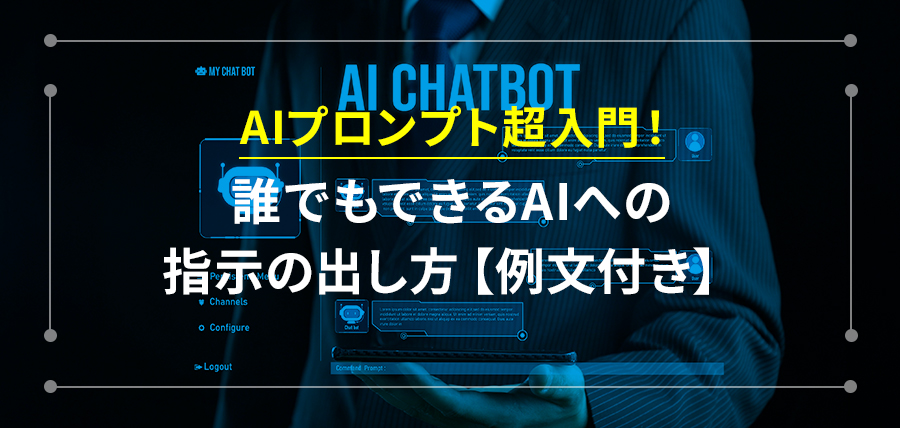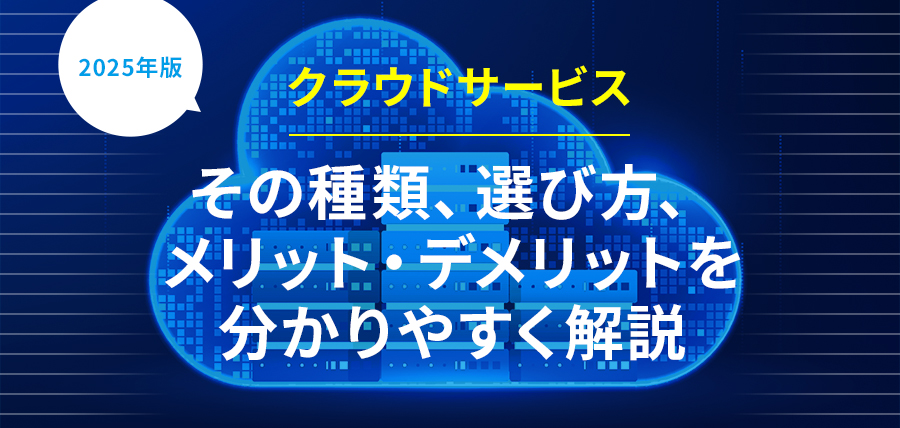経理の自動化を成功させるためには、具体的なステップを知りましょう。よくある失敗を知り、回避策を理解することも必要です。
自動化する業務を見極めて目的を定める
すべての業務を一度に自動化するのではなく、効果の高い業務から段階的に自動化するとスムーズです。どの業務を自動化するかを決めることが、自動化への第一歩です。
まずは、業務フローや担当者、作業にかかる時間などを業務ごとに洗い出し、現状を把握します。そのうえで、効率が悪いものや属人化しているもの、ミスが多発しているものを特定します。その中から、自動化による効果や実現の難易度、経営に及ぼす影響などさまざまな面を考慮して、自動化する業務の優先順位をつけましょう。並行して、自動化せず人の手で行う業務も明確にしておくことも必要です。
自動化によってどのような状態になればよいのかを考え、目的・目標も定めます。例えば「残業時間を月5時間短縮する」「月次決算にかかる日数を3日以内にする」など、数字で測れる目標を設定しましょう。目標の達成度合いを明確に判断できるため、改善策の考案やモチベーションの維持につながります。
自動化する業務を決める際は、実務担当者の意見を聞きましょう。
現場の状況を無視してトップダウンで進めてしまうと、せっかく自動化が実現しても思ったほど効率化されない、逆に業務が複雑になるというリスクもあります。
ツール選定のポイントを押さえる
効率化ツールを選ぶ際は、次のポイントを確認しましょう。
・目的を達成できる機能があるか
・自社の規模や業務内容に合っているか
・期待できる効果にコストが見合っているか
・導入前後のサポート体制はあるか
・既存のシステムと連携できるか
・実務担当者にとって使いやすいか
せっかく費用や手間をかけてツールを導入しても、使いにくかったり目的に沿ったものでなかったりすれば有効活用はできません。コストについては、初期費用や月額料金に加えて、教育にかかるコストなども総合的に考えて判断しましょう。
ベンダーによる導入サポートや、提供者による不具合へのサポートなども事前に確認する必要があります。
複数のツールを比較して検討することも、失敗しないツール選びのコツです。
導入後の運用体制を整える
自動化ツールの導入後は、運用体制を整えて定着させる必要があります。
ツールの運用ルールを決めて、担当者が使い方を習得する機会を設けましょう。運用の手順をマニュアルにまとめることもおすすめです。
ツール運用の責任者や担当者、緊急時の連絡先や対応方法についても明確にしておくと、いざというときに冷静に行動できます。
加えて、ツールのスムーズな導入・運用には現場の理解と協力が不可欠です。従業員の中には、「ツールに仕事を取られる」という危機感や不安を抱く方もいるかもしれません。
モチベーションを保ち、自動化に積極的に協力してもらうために、自動化の必要性や効果について丁寧に伝えることが大切です。
効果測定や改善を重ねながら運用を継続する
ツールの導入後は、効果測定を行い改善や軌道修正を重ねましょう。
導入前に設定した目標と実際の数値を比較して、どの程度達成できたかを測定します。目標を達成できなかった場合は原因を考え、改善策を取る必要があります。
ツールを使う上で出る「こうすればよいのではないか?」「このプロセスは不要ではないか?」という現場の声も運用に活かしましょう。







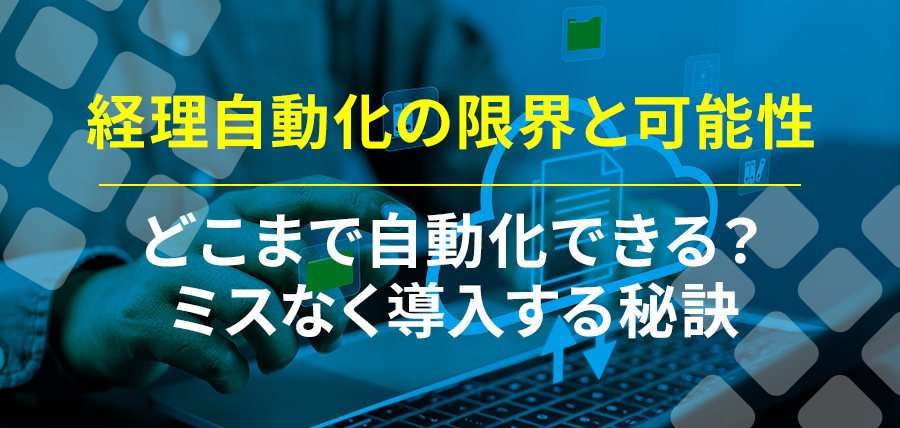





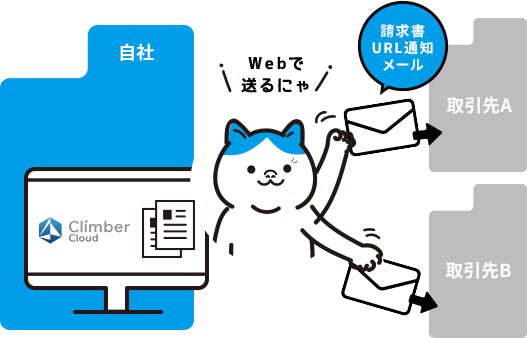
![データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ 自社による保存機能 ]](/article/category_system/img/whatisinvoice/article07_pic03.png)
![データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ Web受領サービス(書類受領) ]](/article/category_system/img/whatisinvoice/article07_pic04.png)