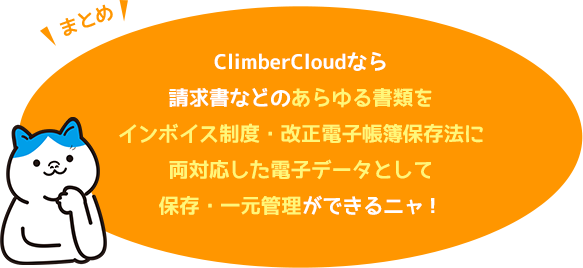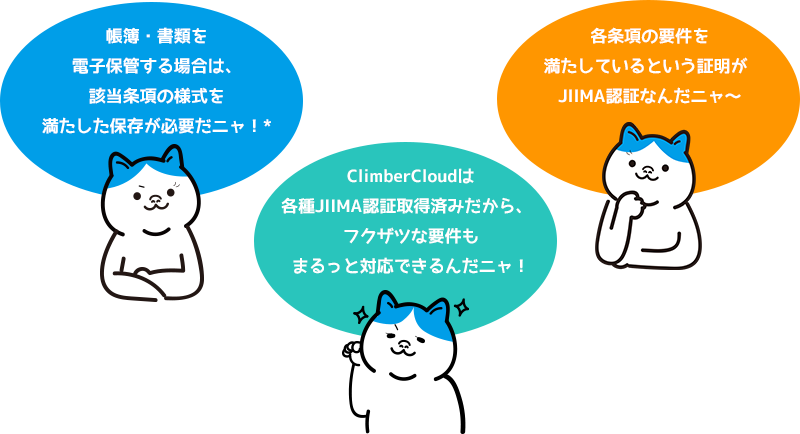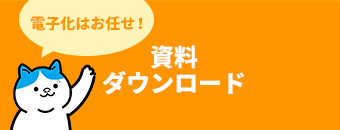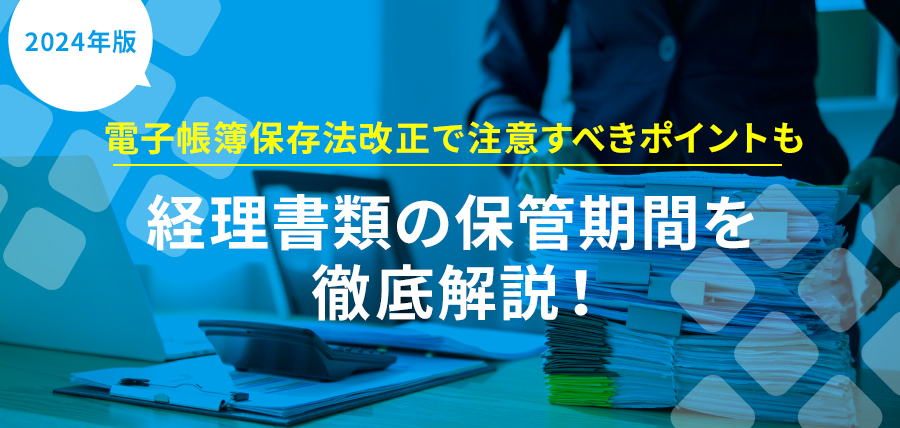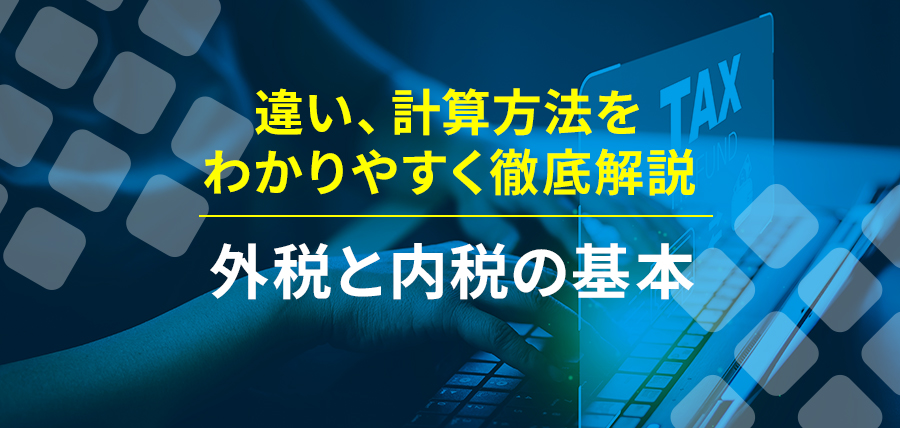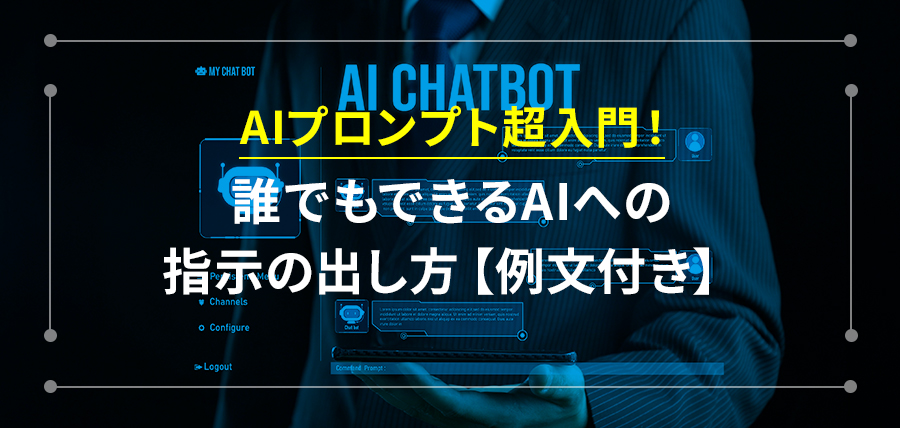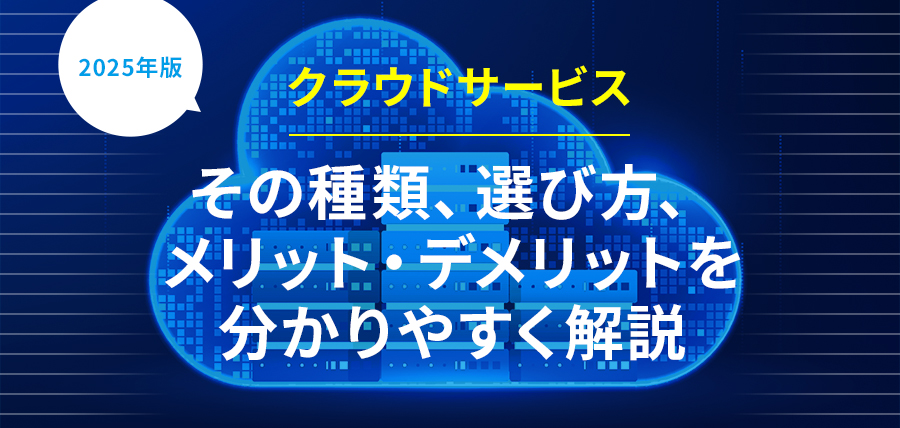01
経理不正の温床となる「落とし穴」とは?手口を徹底解剖

大企業の経理不正は大きく報道されることがありますが、中小企業の場合は内々で処理されることが少なくありません。他社の不正を知る機会が少ないからこそ、主な手口を知っておくと不正を早期発見できます。
売上の水増し
実在しない売上を計上し、売上高を多く見せる方法です。外部に対して業績をよく見せたり、期中のノルマを達成したりするために多く使われます。
売上の水増しを見抜くには、財務諸表や帳簿などの情報と事実が食い違う部分を見つけましょう。例えば、売掛金が不自然に増えていないか、売掛金のもととなる取引の実態はあるかを調査することが有効です。
架空販売による売上の水増しでは商品が動いていないことが多いため、こまめな棚卸による在庫管理も効果的です。
しかし、仕入・在庫・売上の流れの中でどこか矛盾があるはずです。
経費の水増し
虚偽の申請によって、経費を水増しして受け取る方法です。私的利用のお金を経費として申請する、領収書の金額を改ざんして申請するなどの手口が挙げられます。
経費の水増しを見抜くには、経費申請時のチェック体制を強化する必要があります。
資産の着服
企業の資産を自分のものにしてしまう方法です。以下のようにさまざまなパターンがあります。
・財務諸表に計上されない資産を自分のものとする
・棚卸資産・固定資産を私的に使う・売りさばいて換金する
・キックバックを私的に受け取る
経理担当者が一人または少人数の場合は、現金の横領や預金の引き出しは難しくありません。在庫や固定資産を管理している場合は、帳簿を不正に改ざんして私物化することもできてしまいます。こうした資産の管理を一人に任せている場合は、複数人がかかわる管理体制にすることで不正の抑止が可能です。
財務諸表に計上されない資産としては、社員の互助会費や組合費、社員旅行の積立金などが挙げられます。こうした会社の帳簿外で管理する資産については、担当者を持ち回り制にすることが有効です。
キックバックの私的な受け取りには、ダミー会社や経理担当者の身内の会社が使われることが多くあります。
不適切な会計処理
不適切な会計処理には、赤字を黒字と見せかける「粉飾決算」や、黒字を赤字に見せかける「逆粉飾決算」があります。粉飾決算は、利益を大きく見せて信用を保つため、逆粉飾決算は納税額を減らすために多く使われる手口です。
こうした不適切な会計処理に経営層や監査機関が関与していれば、見つけることは困難です。






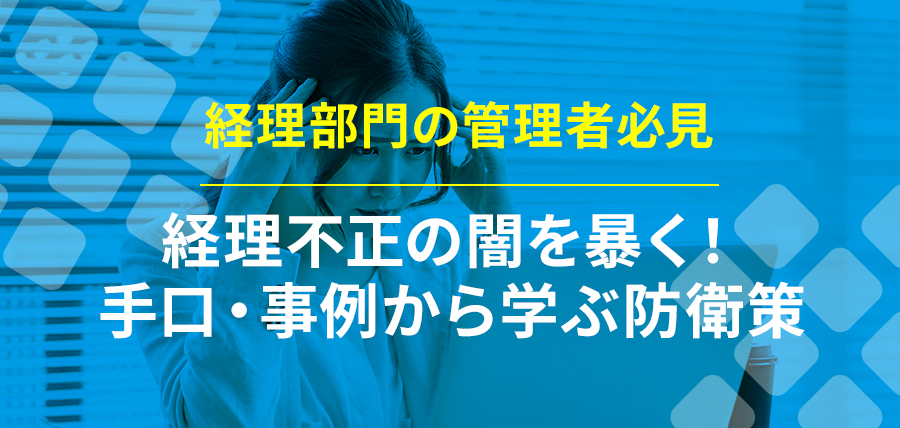




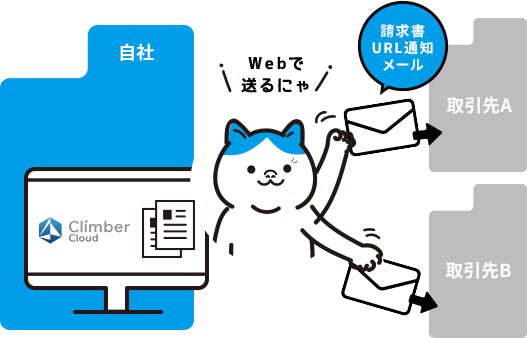
![データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ 自社による保存機能 ]](/article/category_system/img/whatisinvoice/article07_pic03.png)
![データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ Web受領サービス(書類受領) ]](/article/category_system/img/whatisinvoice/article07_pic04.png)