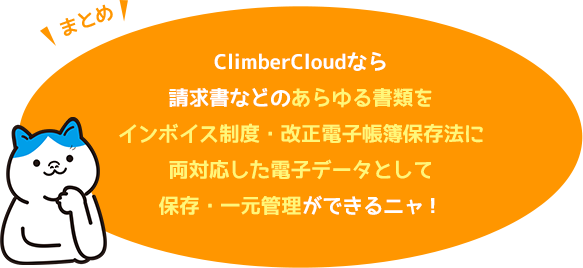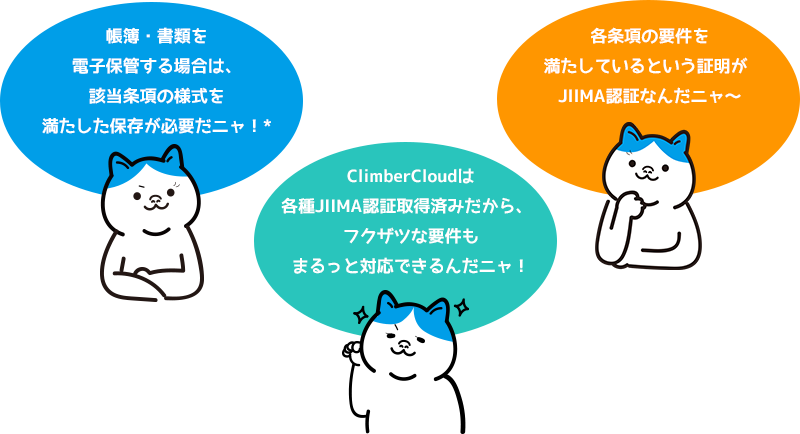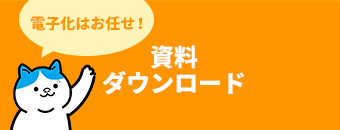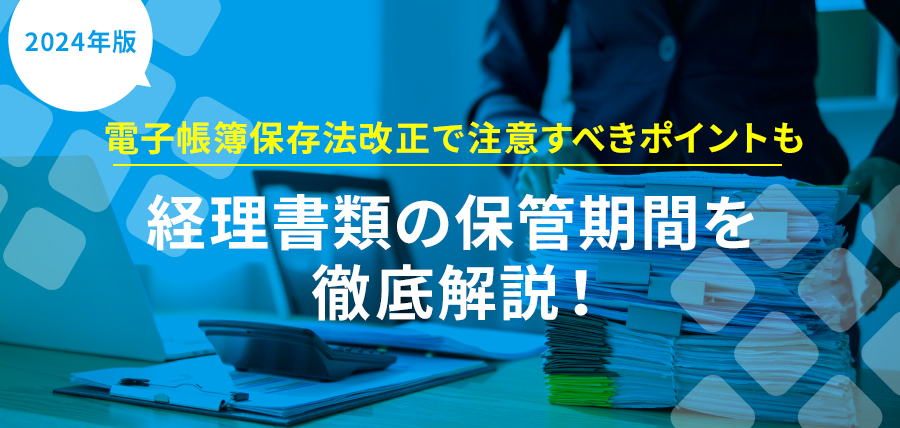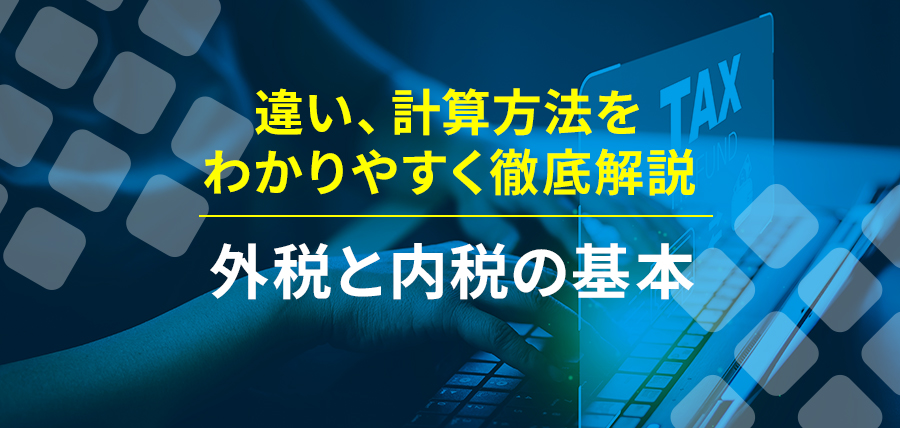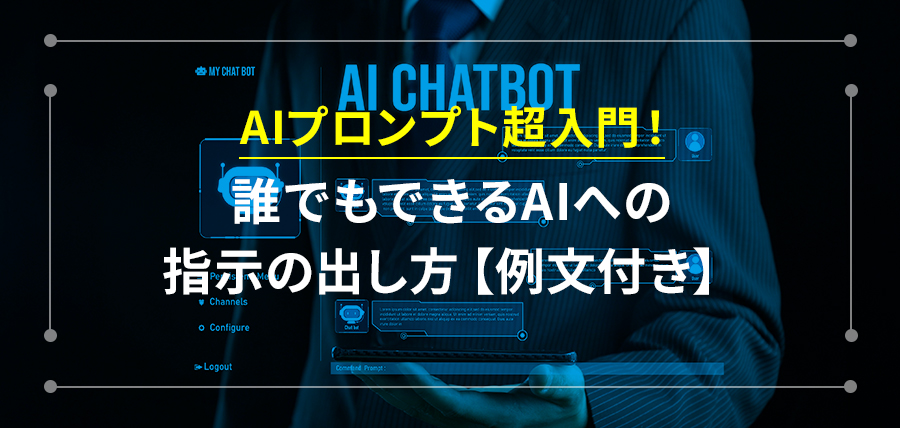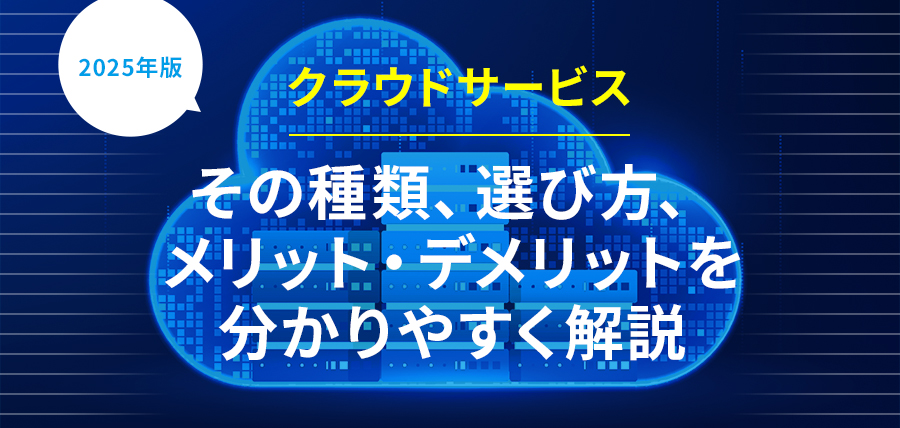01
決算早期化が経営と現場にもたらすメリット

決算早期化は経営層のみでなく、経理の現場にもメリットのある取り組みです。
ここでは各メリットを2つずつ紹介していきます。
【経営メリット①】経営判断のスピード向上
決算結果は経営判断の礎となる情報です。正確な業績のタイムリーな把握は、事業の分析や投資判断の前倒しにつながります。トレンドの変化にも速やかに対応しやすくなり、より小回りのきく経営が可能となるでしょう。
【経営メリット②】ステークホルダーからの信頼向上
決算情報を早期に開示できると、株主や取引先など現在関係している利害関係者のほか、未来の投資家や金融機関などからの信頼の高まりも期待できます。出資や与信の判断においてプラスに作用し、資金調達をしやすくなるでしょう。
【現場メリット①】経理部門の生産性向上
決算早期化に取り組むと、結果として経理部門全体の生産性が向上するでしょう。決算を早期化するためには従来の決算業務の見直しが欠かせず、ミスが少なく効率的に業務を遂行できる体制が整備されるためです。
【現場メリット②】経理担当者の働き方改善
決算早期化への取り組みが、経理担当者の働き方も改善する可能性があります。効率化によって膨大な業務量や残業による担当者のストレスを軽減でき、より健全な労働環境を整えられるためです。






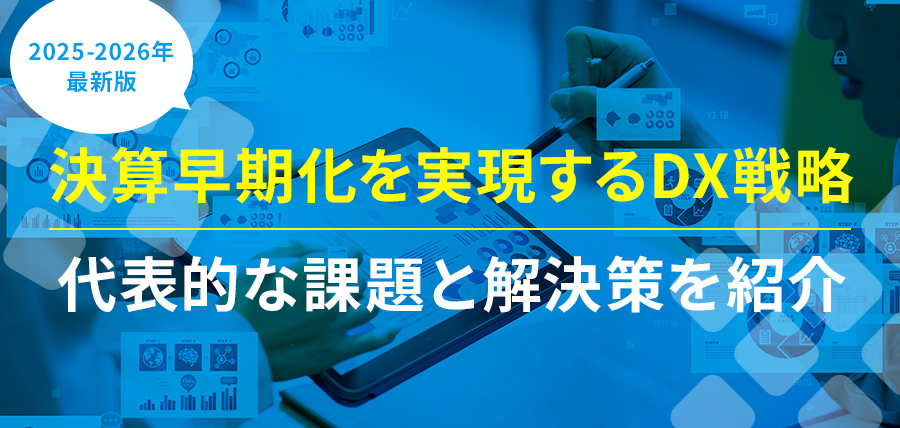





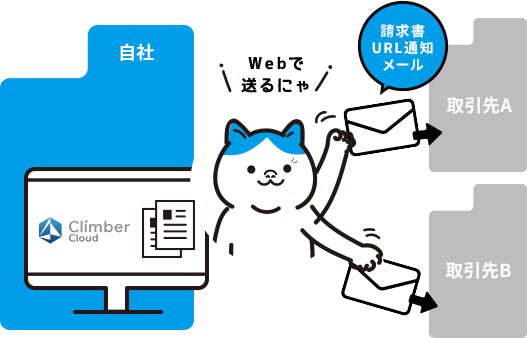
![データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ 自社による保存機能 ]](/article/category_system/img/whatisinvoice/article07_pic03.png)
![データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ Web受領サービス(書類受領) ]](/article/category_system/img/whatisinvoice/article07_pic04.png)