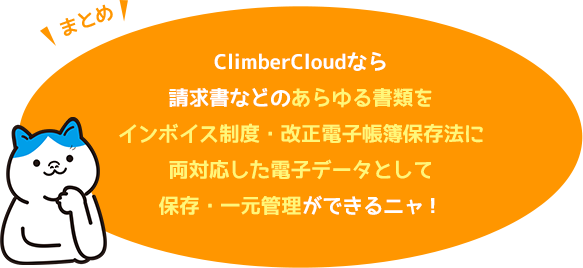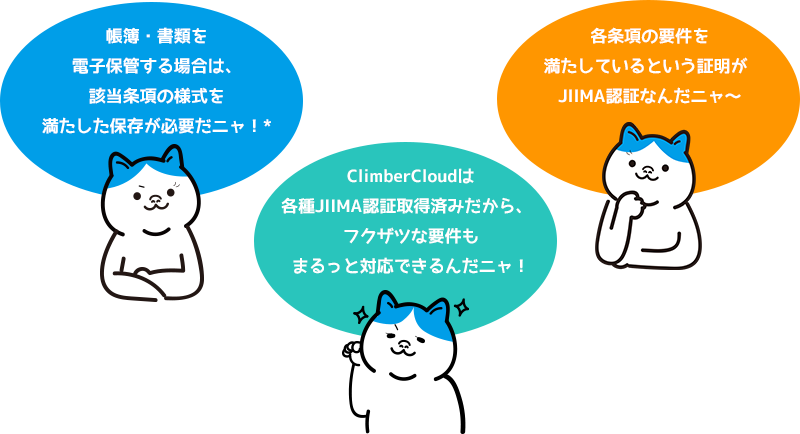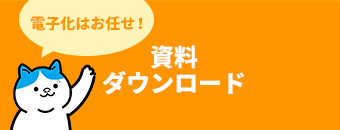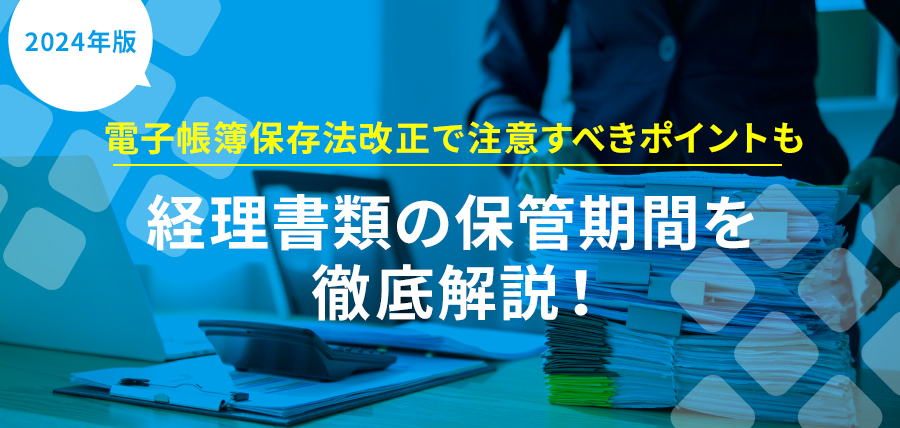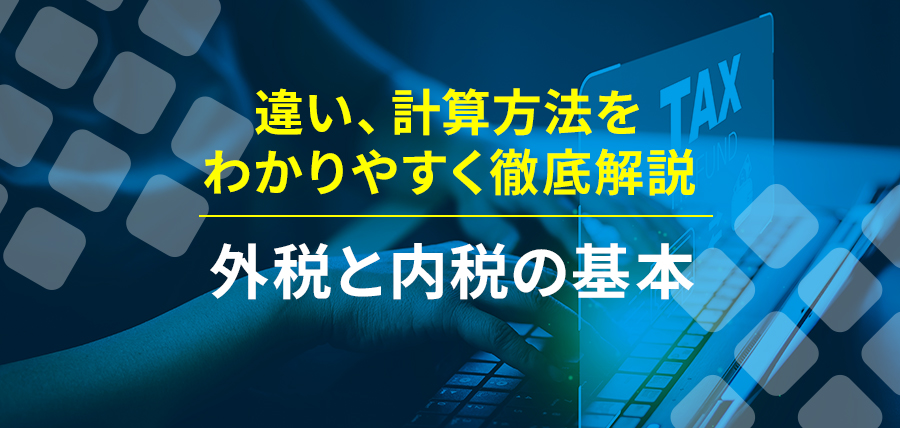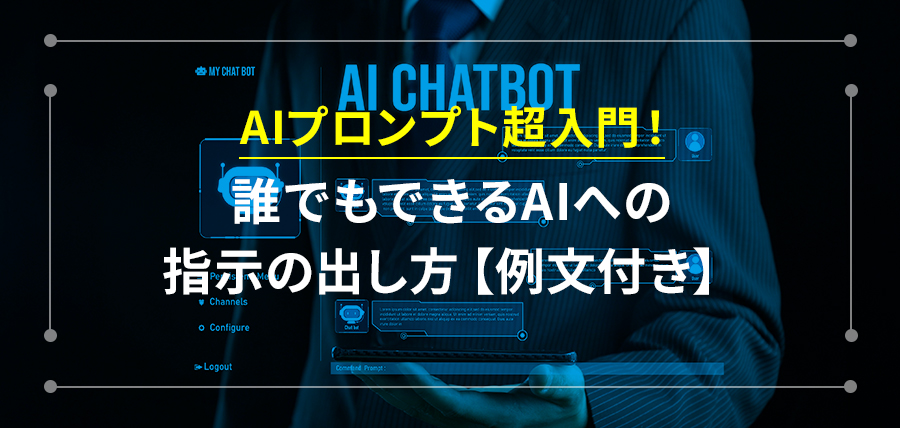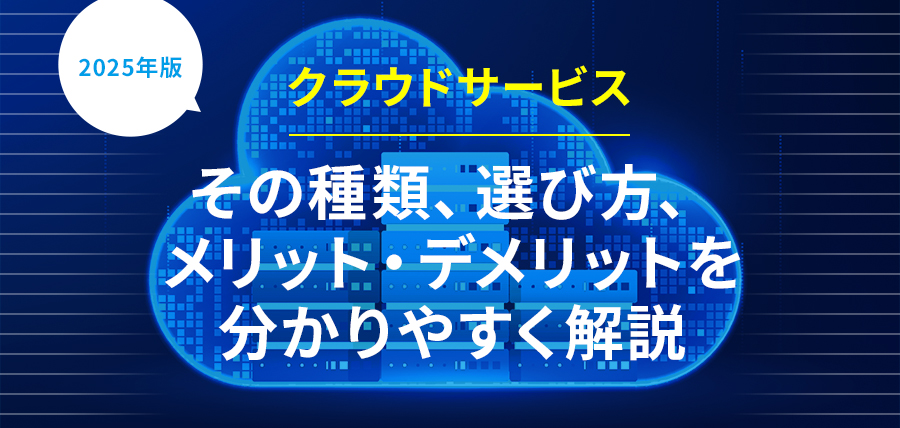01
ここが危ない!経理の属人化のリスクと発生しやすいポイント

経理業務が属人化することで、様々なリスクが発生します。属人化の具体例や陥りやすい理由を知り、対策の必要性を確認しましょう。属人化の恐れがあるかどうかを確認できるチェックリストもぜひご活用ください。
経理の属人化によるリスク
経理の属人化には、次のリスクがあります。
・担当者以外が進捗状況を把握できない
・ミスや不正を発見しにくい
・退職や異動によりノウハウ・知識が失われる
・担当者の負担が大きい
・業務改善や効率化がしにくい
・人材採用のハードルが上がる
こうしたリスクは、業務を遂行できる人が限られてしまうがために起こります。経理に関する知識やノウハウが特定の人に集中することは、「あの人が全部わかっている」という安心感につながる一方で、すべてがその人頼みの危険な状態となっているともいえます。
客観的な視点が入らずブラックボックス化することで、ミスの発見が遅れる、不正の温床となるなどの恐れがあります。
経理で属人化が起こりやすい要因
経理業務には、属人化を招きやすい次のような要素があります。
・業務の専門性が高い
・暗黙知が多く説明するのが難しい
経理業務の経験が長い担当者であれば、感覚で処理できる部分もあるため、わざわざ他人と共有できる形でマニュアルを作成していないことが多いでしょう。また、経理業務には細かな「暗黙知」が多いことも、属人化しやすい理由のひとつです。
担当者本人が属人化を問題ととらえていない場合もあります。担当者は「人に教えるより自分がやった方が早い」「教えている時間がもったいない」と思っているかもしれません。「自分しかできない業務がある」という立場を維持したいがために、業務内容をほかの従業員と共有したくない担当者もいるでしょう。
経理の暗黙知の具体例
経理における暗黙知には、次のものが挙げられます。
| 経費精算 |
・イレギュラーな処理 ・例外への対応 |
| 月次・年次決算 |
・仕訳判断 ・調整業務 |
| 資金繰り | ・金融機関との交渉 ・予測の立て方 |
| 税務申告 | ・税法改正への対応 ・複雑な特例 |
| 固定資産管理 | ・取得・売却時の特殊処理 |
| 給与計算 | ・法改正への対応 ・社会保険・労働保険に関する処理 |
経理業務は多岐にわたります。誰にでもわかる形に言語化・図式化することが難しい業務やプロセスが多くあることも、経理の属人化の原因のひとつです。
あなたの部署に当てはまる?属人化度チェックリスト
属人化が発生する主な要因には、次のものがあります。自分の部署に該当するものがないか、チェックしてみましょう。
-
担当者が1人である
-
特定の人でなければできない業務がある
-
担当者が休みを取ると進まない業務がある
-
業務のマニュアルがない
-
複数人によるダブルチェックの体制がない
-
担当者がノウハウの共有や属人化の解消に消極的
-
担当者が経営者・他の従業員と情報共有をする仕組みがない






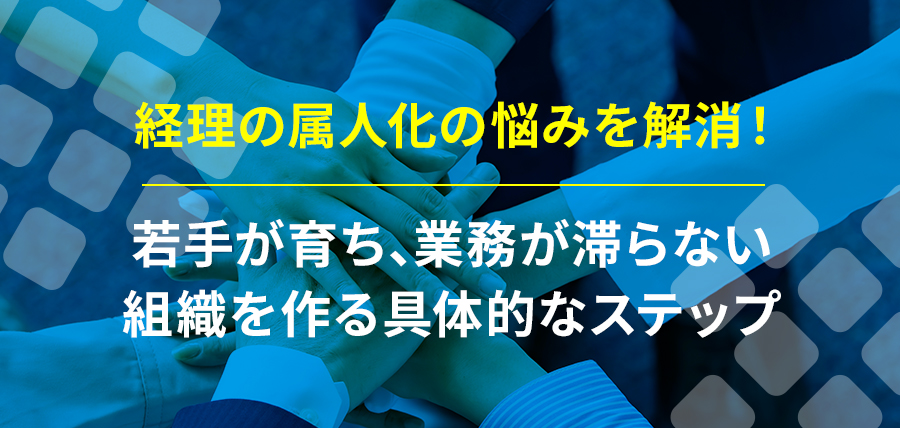





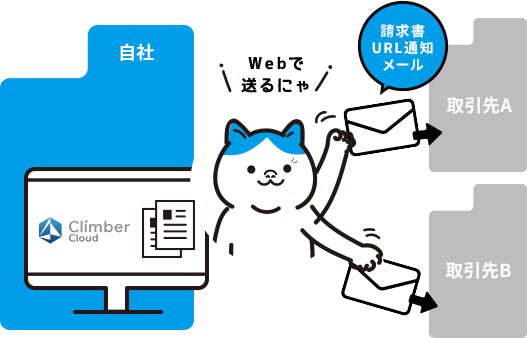
![データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ 自社による保存機能 ]](/article/category_system/img/whatisinvoice/article07_pic03.png)
![データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ Web受領サービス(書類受領) ]](/article/category_system/img/whatisinvoice/article07_pic04.png)