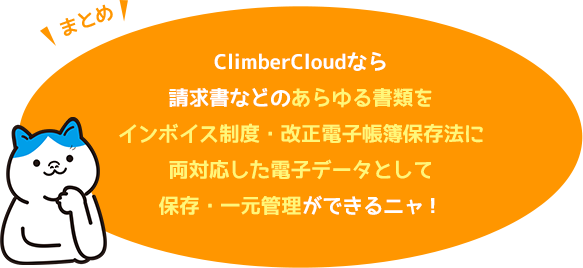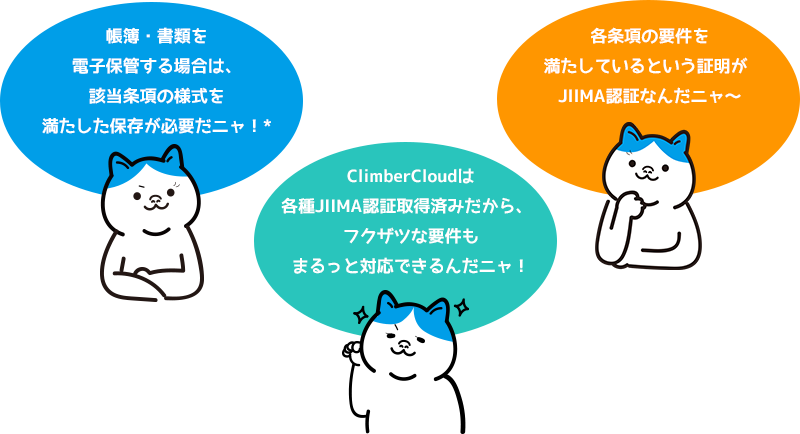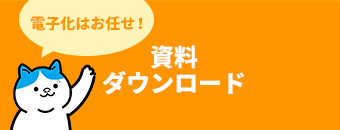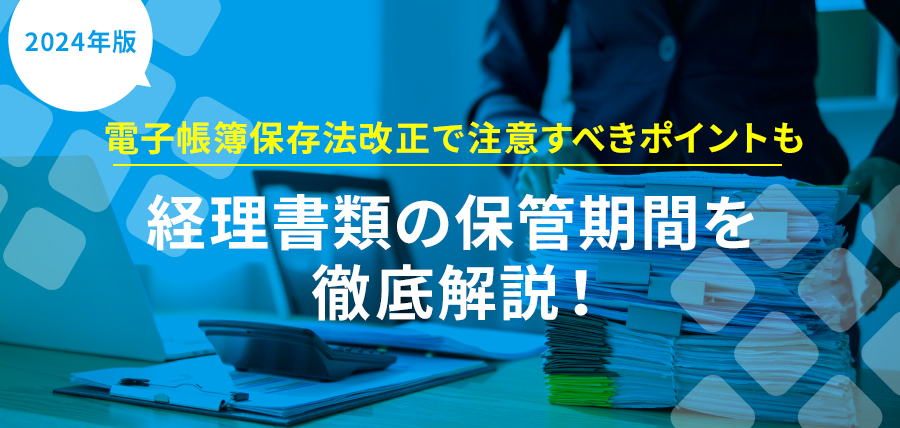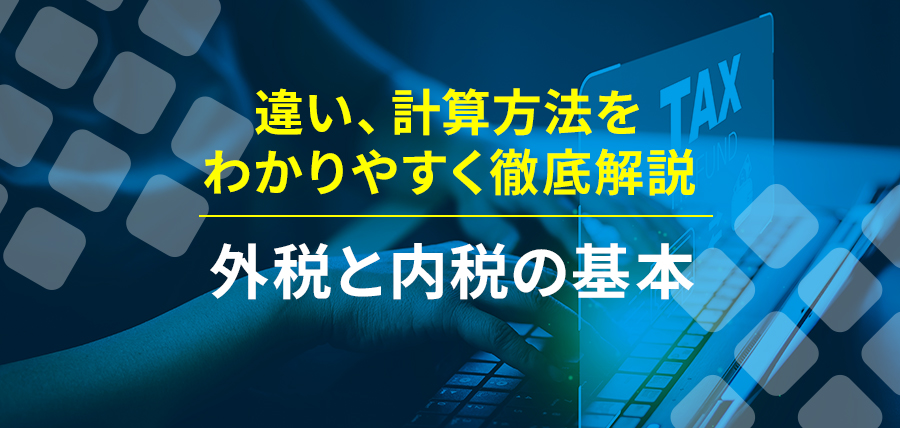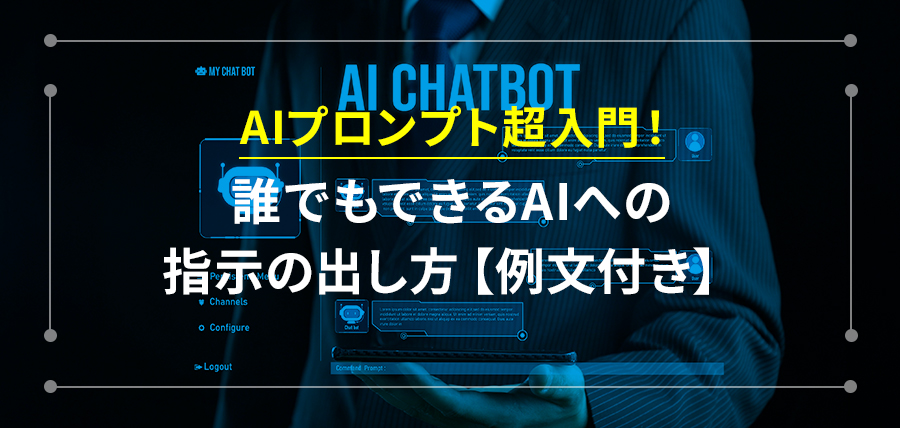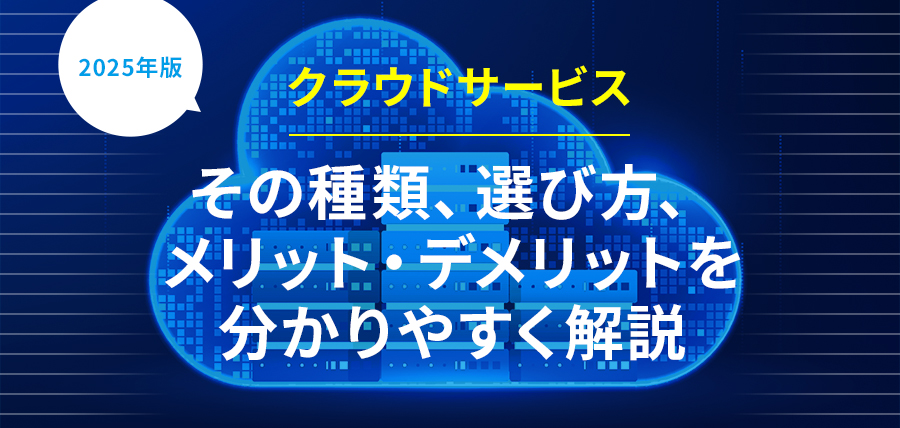01
なぜ電子取引データの訂正・削除防止が必要なのか?

まずは、電子帳簿保存法における電子取引データについての定めと、電子取引データの不当な訂正・削除によるリスクを整理しましょう。
電子帳簿保存法の概要と改正点
電子帳簿保存法は、税務に関する帳簿や書類を電子データとして保存するルールを定めた法律です。2024年以降の電子取引は、データ形式での保存が完全義務化され、紙での保存は認められなくなりました。
電子取引データの重要性
電子取引データとは、これまでに紙でのやりとりでも保存が必要だった帳簿書類のデータ版です。例えば、請求書、領収書、契約書、見積書などが挙げられます。
これらの書類は、紙からデータへ形式が変わっても、取引の事実を証明する重要な証拠であり、会計の基礎となる点は変わりません。法人の場合は受け取ったデータだけでなく送信したデータも含めて7年間の保存義務があります。
訂正・削除によるリスク
電子取引データの不当な訂正や削除は、法的なリスクを伴うほか、会計処理の誤りから各種トラブルにつながりかねません。
法的リスクとしては、青色申告の承認が取り消されるおそれがあります。
電子取引データ保存の具体的な課題やリスク
電子取引データの保存先としては、クラウドストレージやHDDが代表的です。こうした方法を使ってデータを保存する際、多くの企業が感じている課題やリスクは下記のとおりです。
・PCの不具合などによりデータが消失する
・外部からの不正アクセスやマルウェアによりデータが改ざんされる






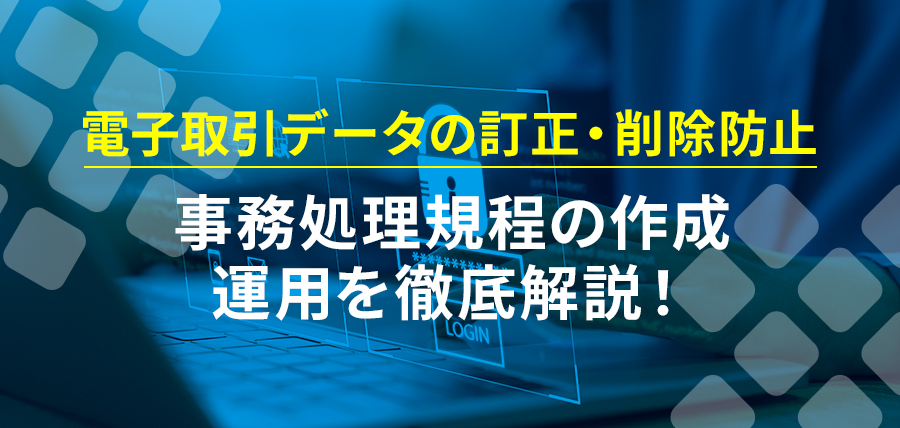
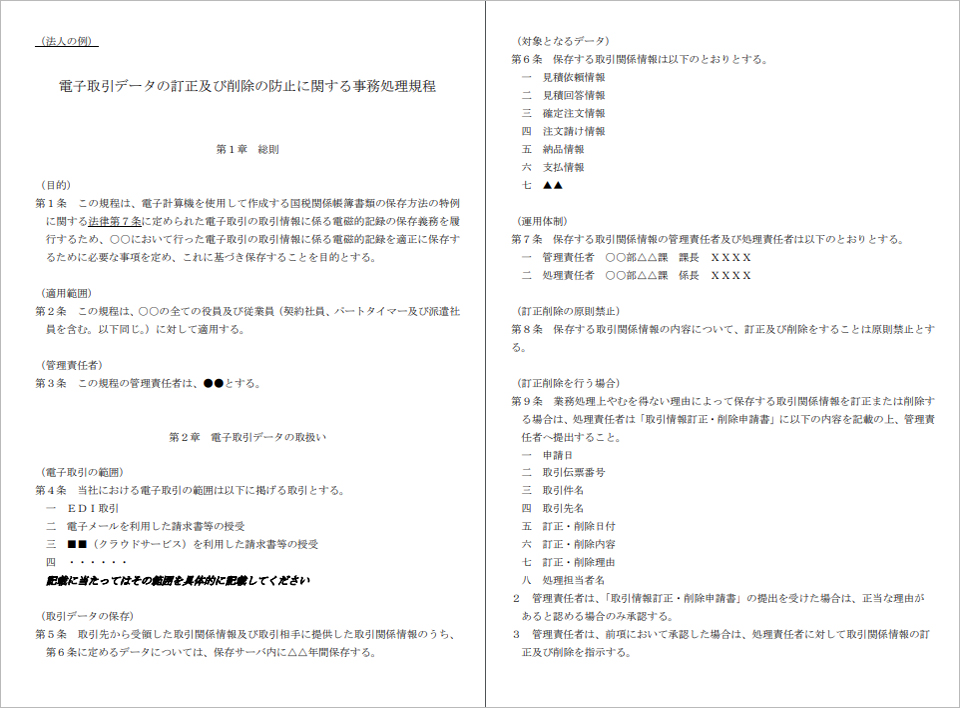





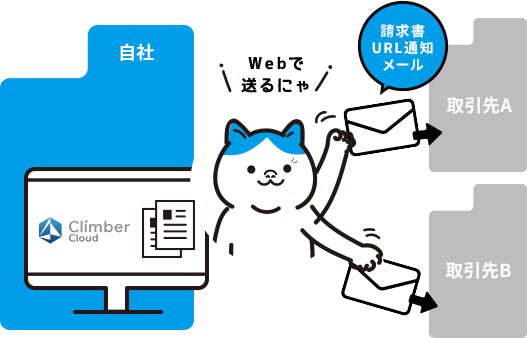
![データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ 自社による保存機能 ]](/article/category_system/img/whatisinvoice/article07_pic03.png)
![データ保存サービス(電子帳簿保存法対応)[ Web受領サービス(書類受領) ]](/article/category_system/img/whatisinvoice/article07_pic04.png)